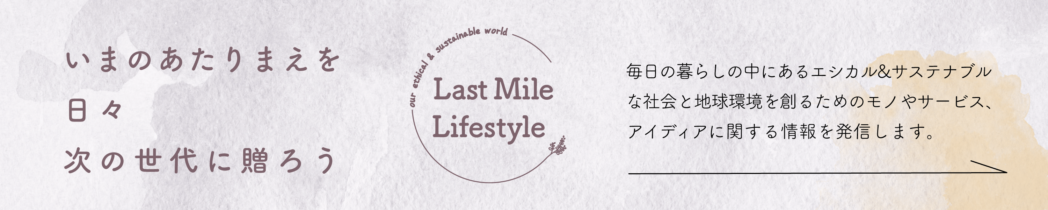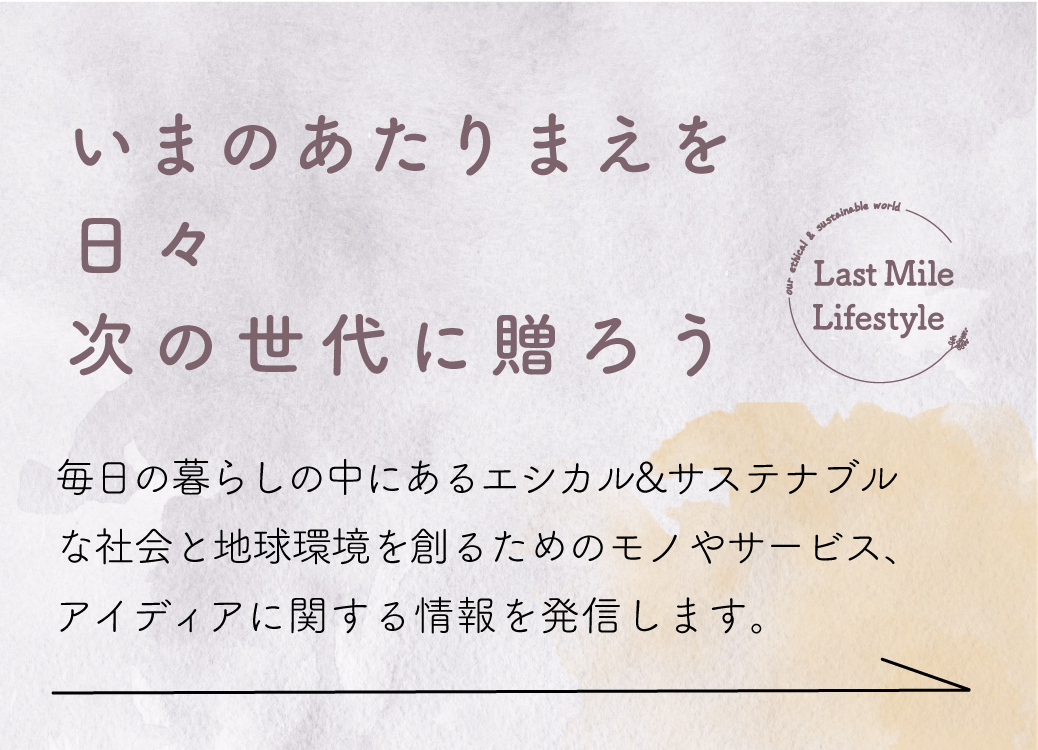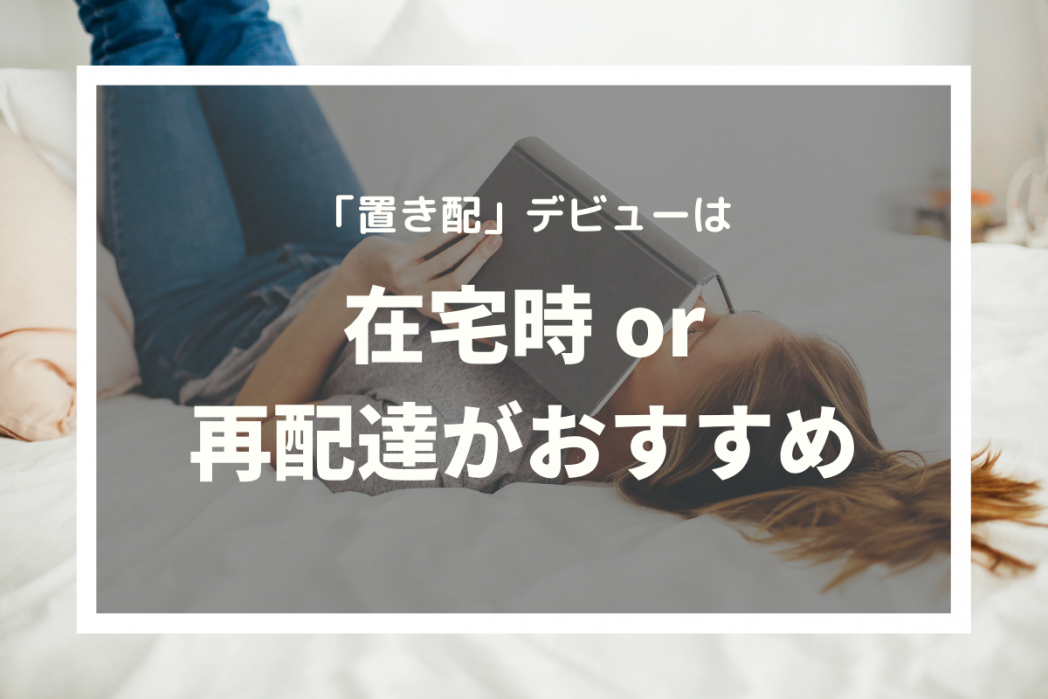さて、今回は「置き配」デビューの前に気を付けたいポイントをチェックリストにしてみました。
OKIPPAバッグはポスト投函で配達されますので、バッグが届いたらまずは中身を確認しましょう。

(※鍵の形状や色が異なる場合があります。)
説明書をお手元にご用意いただきながら、ひとつずつ、利用開始前のポイントをご紹介していきたいと思います。


OKIPPAバッグの初期設定

まずは説明書の通りに確認していきましょう。今回は基本の設定を中心にご紹介します。
ここでは、OKIPPAバッグの設置で注意したいポイントをチェックリスト(10項目)にまとめました。
OKIPPAバッグを利用するためのチェックリスト
| ✔︎①: | 付属品(専用ロック・ダイヤル式南京錠・結束バンド・シール・プラカード・説明書)は全て確認しましたか? |
| ✔︎②: | 専用ロックの暗唱番号は設定しましたか? |
| ✔︎➂: | ダイヤル式南京錠の暗唱番号は設定しましたか? |
| ✔︎④: | OKIPPAバッグの畳み方・広げ方は確認しましたか? |
| ✔︎⑤: | 専用ロックの操作方法の確認はしましたか? |
| ✔︎⑥: | 専用ロックにシールを貼りましたか? |
| ✔︎⑦: | 専用ロックのワイヤーを正しく固定できましたか? |
| ✔︎⑧: | OKIPPAバッグに専用ロック・ダイヤル式南京錠を正しく取りつけられましたか? |
| ✔︎⑨: | OKIPPAバッグに「配達員向けプラカード」を取りつけましたか? |
| ✔︎⑩: | OKIPPAアプリ※をダウンロードできましたか? ※荷物追跡サービスを含むOKIPPA公式アプリは2022年1月31日にサービス終了いたしました。(2022/3) |
10項目が確認できたら、専用ロックのワイヤーを引き出し、玄関のドアノブ、蝶番、格子などを利用してしっかり固定します。
専用ロックには付属のシール(ここを押して上部のワイヤーを伸ばしてください)を必ず貼っておきましょう。
このメッセージを貼っておくと、荷物を預け入れる際、配達員の方がスムーズに専用ロックの操作を行えます。
専用ロックがセットできたら、置き配バッグOKIPPAを吊り下げて設置します。
「配達員向けプラカード」の取りつけも忘れずに行いましょう。
(※詳しくは説明書の図もご覧ください)
これでひとまず設置は完了です!
次は、利用を開始する前に特に注意したいポイントをお伝えしていきます。
専用ロックとダイヤル式南京錠の設定・設置方法は要チェック!
【暗証番号の設定】
専用ロックもダイヤル式南京錠も、サイド下部にリセットボタン(穴)があります。その穴をドライバーやペン等で押しながらダイヤルを回し、好きな番号に設定しましょう。番号を合わせるときは、リセットボタンを押したままです。

リセットボタンを話すとセット完了になります。その後、動作に問題がないかをテストします。
専用ロックもダイヤル式南京錠も、配達された荷物を守るための大切な鍵ですので、専用ロックの暗唱番号とダイヤル式南京錠の暗証番号は別のものにしておくと安心ですね。
(例)専用ロックの暗証番号を『123』とした場合は、ダイヤル式南京錠では『123』以外にするなど。
【専用ロック】
専用ロックにはワイヤーが内蔵されています。上部にあるワイヤーは本体のサイドにあるボタンで引き延ばしたり縮めたりすることができます。下部のワイヤーは暗証番号を合わせた状態でサイド下部のボタンを押すと解錠できます。

サイド下部のボタンを押すと短いワイヤーを差し込み口から引き出すことができますので、そのワイヤーをOKIPPAバッグ上部にあるタブに通します。その後、再び差し込み口にワイヤーをセットしダイヤルを回せば、バッグ本体と専用ロックを固定することができます。
【ダイヤル式南京錠】
ダイヤル式南京錠は、OKIPPAバッグのファスナーを閉め合せたときにできるリングに「掛け金」に開けた状態で通します。

配達員の方は荷物を預け入れた後にダイヤルを回し施錠します。掛け金を閉めてセットしてしまうと、配達員の方が誤ってロックしてしまうなど、荷物を入れられなくなることがありますのでご注意ください。
設定、設置方法についてはこちらもご確認ください
宅配ボックス(宅配バッグ)へ「配達希望」の意思表示
配送を依頼する際、お届け先の氏名・住所・会社名・メモ欄のどれかに「OKIPPA使用の可否」を記入する必
要があります。
○バッグ内への配達を希望する場合:「不在時OKIPPA預入希望」
○バッグ内への配達を希望しない場合:「OKIPPA預入不可」
OKIPPAへの置き配を希望する場合は、受取人の意志を「お届け先情報」に明記しておくことで、「直接手
渡しでなくて良いので、指定したバッグ内に配達してください」というメッセージを発することができます
≪注意事項≫
販売元が宅配ボックス預入不可と指定している場合は、OKIPPAバッグ内へ配達してもらうことができません。また、配送業者が預入不可と判断した場合はバッグ内への配達ができないことがあります。
設置方法と手順を守れば「置き配」は成功します!
宅配便を取り扱うにあたって各運送会社は、国の許可を得た「宅配便運送約款」という規則に基づき配達業務を行っています。例えば、「宅配ボックス」の利用にあたっては、安全な「管理」や「保管」が可能だと判断できた宅配ボックスには配達可、などのルールが決められています。
そのため、ワイヤーの固定がしっかりとされていなかったり、安全だと判断できない場合には、置き配をしてもらえず不在連絡票での対応となることがあります。また、受取人の住所であることが確認できない場合(表札等の記載がない場合)には、預入をしないこともあります。
≪注意事項≫
冷蔵品・冷凍品・食品は預入ができません。
宅配バッグOKIPPAのサイズを超えるものは預入ができません。
設置方法と手順を守れば、確実に「置き配」をしてもらうことができますので、今回ご紹介した最初の準備を行いながら設定していただけると幸いです。
宅配便運送約款についてはこちらの記事もご参照ください↓
最近では、国交省や環境省も「置き配」に前向きな動きを見せており、各運送会社やECサイト、宅配ボックスの販売事業者と共に、「置き配検討会」を開いて普及に向けた取り組みを行っています。
(実は、Yper株式会社の代表も、この検討会のメンバーになっています!)
次回からは、OKIPPAバッグ開始時のコツや裏ワザも、たっぷりご紹介していきますので、楽しみにお待ちください。
OKIPPAについて詳しく知りたい方へ
非対面での宅配物の受け取り、もう荷物を待つ必要はありません。